-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日、補強土壁研修がオンラインにて行われました。
同研修は、毎年【公益財団法人 宮崎県建設技術推進機構】主催で行われています。
主な内容は、補強土壁工法の概要、設計施工条件、調査と管理、崩壊・変状の原因と対策です。
特に興味深かったのが『崩壊・変状の原因と対策』でした。
崩壊・変状などの災害は「誘因」が「素因」に作用して発生するそうです。
素因:その土地が持っている災害に関わる性質(地形,地質,気候等)
誘因:災害を発生させる直接的な引き金(地震、豪雨等)
素因には多様な原因となるものがありますが、誘因は主に大雨と地震だそうです。
昨今の日本は、スコールみたいな豪雨や、東日本大震災や能登半島地震のような大地震が頻繁に発生しているように感じます。
このような気候変動や地震の発生を防止することは不可能ですが、その場所の地形や地質、気候等を把握し、いかに素因となりうる原因を除去することが災害減少につながるかが理解できました。
弊社は社会資本整備に関わる企業です。会社としても技術者としても誇り高い志を持ち、皆様が快適で安全な社会生活が送れるよう微力ながらお手伝いが出来ればと思いました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
昨日、福岡まで公共測量技術講習会【三次元点群測量】に参加してきました。
当講習会は、日本測量協会が主催し東京を拠点として全国でWeb方式にて行われました。
最近の測量は、ある意味点群データをどのように活用するかにかかっていると思います。
弊社は、2018年に地上型レーザスキャナを、2022年にUAVレーザスキャナを導入しました。

狭い範囲はこれにお任せ
トプコン TLS-2000

広い範囲はこれにお任せ
Matrice300RTK
ここ数年は地上型レーザスキャナを主軸とし、点群データより平面図や縦横断図を作成しています。
先月納品した測量業務も点群データより縦横断図を作成しました。
三次元点群データは、沢山の点(XYZ)の集合体で構成されたデータで、その点一つ一つに色や受光強度といった情報を付与したものであり、色情報を付与したデータはさながら画面の中のちっちゃな箱庭のようです。
地上型レーザスキャナ、UAVレーザスキャナともに普及が進んでおり、利用頻度も日に日に増加しています。
昨年の日本測量協会での三次元点群測量成果検定件数は249件と年々増加しており、中でもUAVレーザ測量が群を抜いて増加しているようです。
今後、こういった測量機器が主流になるかと思いますが、旧来の測量機器も大事にしつつ新しい技術も取り入れていかねばと思う測量オタクなおじさんでした。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日、『ジオスぺ―シャルフェア2024』に参加してきました。
このフェアでは、ニコントリンブルの最新機器の展示やデモンストレーション、セミナーなどが開催され、どれも興味深いものばかりでした。

特に興味があったのは、業界でも深刻な2024年・2025年問題でした。
今後、労働時間の短縮や人口減少に伴い、担い手不足が加速すると考えられており、人員確保やAIの活用が期待されます。
特に、昨今の測量機器やPCソフトの発展は目覚ましく、人の経験からAIに移行しており、誰でも作業結果が同じになるということでした。
こういった測量機器やAIを活用することにより、今後起こりうる人手不足をいかに解決していくかが重要であると分かるセミナーでした。

3Dスキャナー一体型のTSです。視準はタブレットPCで行う優れもの。

スマホを使っての3Dスキャニングシステム。とりあえず街を歩けば3次元点群データが出来ていきます。今後はちょっとそこまでな散歩感覚の測量も可能?

巷で話題のドローン。
とにかくデカい。かなりデカい。けど、もうこれがないと仕事ができないという今日この頃。
つい最近田んぼの上をドローンが飛行していて、何しているのかと思ったら農薬散布中でした。いたるところでドローン大活躍です。
こんにちは。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
これまでグルメ特集でしたが、今回は七夕についてお話をしようと思います。
先日我が家で七夕をしました。
不器用なのですが、飾りを作ってみました♪
飾りには意味があるのをご存でしょうか?

【星飾り】
願いが星のある天まで届くように
【輪つなぎ】
星が連なる天の川から連想させ
人とのつながりや夢が続いてく
など他にも色々な意味がこめられているそうです。
ちなみに、私が何を短冊に書いたかは秘密ですが・・・。
短冊には、習い事や勉強など成し遂げられる夢や目標を願うといいそうです。
目標をもって仕事をすることは大切であると、七夕の飾りつけをしながら
しみじみ感じることができたそんな七夕の日でした。
毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
暑い夏こそ、美味しい食べ物を食べて元気をつけようと
先週、宮崎県の最南端にある串間市を訪ねました。
串間市は、魚のぶりやサツマイモの産地として有名です。
【ぶりプリ丼】
ぶりにかけるタレはネギの醤油と味噌です。2種類の楽しみが味わえます。

【串パフェ】
パフェの具材は、マンゴー マンゴージャム あくまき 金柑シャーベット かりんとうなどすべて串間産です。
宮崎県26市対抗ご当地グルメコンテストにて優勝したことのあるスイーツだそうです♪
どうりで、美味しかったです(^▽^)/

これから猛暑が続き、体調を崩しがちですが、美味しいものを食べて体力をつけ仕事を頑張ろうと思える休日でした。
皆さんも、美味しいものを食べて、栄養をつけましょう。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
梅雨時期特有の蒸した天気で体調は崩されていないでしょうか。
さて本日は、週末の休みを利用して土木遺産巡りをしてきました。
最初訪れた箇所はこちら。

これなんだかわかりますか?
こちら、熊本県山都町にある円形分水というものです。
この装置は、1956年(昭和31年)に現代土木工学により完成し、水田の面積に応じて水を配分するよう工夫されているそうです。
この円形分水、笹原川から水を取り込み、装置手前でサイフォンにより円形の真下から水が湧き出るような構造となっており、湧き出た水を仕切り板で約8:2の割合で配分しています。
昔の人の知恵はすごいと感心しました。
さて続いて訪れた場所は円形分水にて分けられた水の行先『通潤橋』です。

こちらの通潤橋は1854年(嘉永7年)に農業用水を送るために建設された近世最大級の石造単アーチ橋で、石工の技術レベルの高さを証明する歴史的建造物とし、1960年(昭和35年)に国の重要文化財に指定され、なんと2023年(令和5年)国宝に指定されました。
1854年は今から170年前、江戸時代、徳川幕府の時代で黒船来航の翌年です。
(1854年が江戸時代とも知らず、おじさんは歴史が不得手なのでネットで検索しまくりです。)

それにしても見事な石の並び。惚れ惚れします。
この石、よく落ちないなと御思いの方がいらっしゃると思いますが、一番上の真ん中の要石を一個とるだけでバランスが壊れすぐさま崩落します。
※詳しいことは通潤橋そばの資料館へ。
通潤橋は、2016年4月の熊本地震で橋の上の損傷に加え、2018年5月の豪雨で石垣が崩落し補修工事を行っていたようです。
2020年には4年ぶりに放水を再開し、今もなお現役として水田を潤している本当に素晴らしい土木建造物ですね。
この日は天気も悪く、農業用水として利用されているため放水はありませんでしたが、7月中旬には放水を再開するみたいなのでその時にでもまた訪れようと思います。
皆様も、昔の人の知恵と努力の結晶を見に行かれてはどうでしょうか。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
本日は、県土木事務所及び各測量業者を集めた大規模災害対応講習会が開催されました。
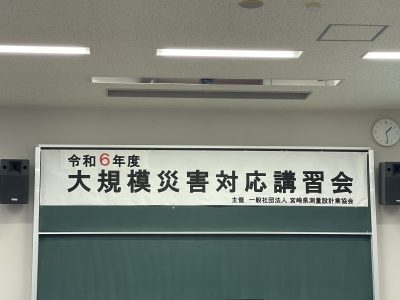
本講習会は毎年開催され、弊社からは3人参加いたしました。
講習内容としては、近年の災害発生状況や大規模災害発生時の協定内容、連絡体制の確認などがありました。
特に、自分自身興味があったのが安全管理です。
近年、労働災害による死亡者数は減少傾向である一方、死傷者数は横這い傾向となっています。
これからの時期は、宮崎県では特に梅雨や台風など水害の多く発生する季節です。
最近では、宮崎県でも川で作業していた測量作業員が1名亡くなったばかりです。
皆様も今一度安全管理について考えてはいかがでしょうか。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
本日6月3日は『測量の日』です。
『測量の日』とは、昭和24年6月3日に測量法が公布され平成元年に制定された測量の記念日です。
私も測量という仕事に携わり早30年以上経ちますが、昨今の技術の進歩は凄まじく早く感じます。
30年前は電卓片手に現場で測量することが多く、図面もトレースが当たり前でした。
それがCADの普及に始まり、トランシットの自動化、GNSS測量(衛星を使用する測量。皆さまおなじみの車のナビゲーション)、しいては測量データの3次元化やUAVを使用しての効率化。
世の変化についていくのがやっとというところです。
こういう日には、昔の測量機器や測量方法を懐かしむのもいいかもですね。
(若い技術屋に昔の話をすると煙たがられますのでほどほどに)